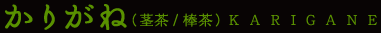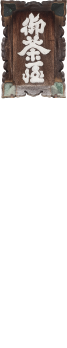
鎌倉時代初期、栄西禅師が宋から持ち帰った茶の種子を明恵上人が栂尾深瀬に播き育てた後、茶の普及の為に宇治に移植したことに始まります。室町時代には、足利義満が宇治茶の栽培を奨励し、室町幕府の御用茶園「宇治七名園」を開かせた頃には、栂尾にかわって宇治が茶の本場となります。織田信長、豊臣秀吉の時代も、宇治茶は保護されました。
江戸時代に入ると朝廷や幕府への献上が続き、三代将軍 徳川家光は朝廷献上茶と将軍家直用の高級茶を作らせ、江戸までの新茶の運搬を「お茶壺道中」として制度化し、以来250年間続けられます。宇治の茶師たちは、この「お茶壺道中」の中核的な担い手として携わり、日本茶文化を長く支え続けました。
1738年 宇治田原の永谷宗圓により新しい製茶法、蒸した茶の新芽を焙炉の上で揉み乾燥させる、画期的な「宇治製法(青製煎茶法)」が生み出されました。これが現在の日本茶(煎茶)の始まりです。
1835年には宇治小倉の茶師木下吉左衛門が偶然に生み出したといわれる玉露。玉露はのちに宇治の辻利右衛門によって完成されました。
日本最古の生産地としての伝統と、宇治川がもたらす川霧・豊かな土壌、自然条件、製茶技術の高さで、生産量は多くはないですが、上質な茶を生産し日本の代表的産地となっています。

-
一番茶の新芽が伸びだした頃、茶摘みの20日以上前から茶園に覆いをかけ日光を遮った茶園で柔らかく、緑色の濃い芽を育てます。
その新芽を蒸した後、揉まずに乾燥させた碾茶を茶臼で挽いたものが抹茶です。
お茶の栄養成分全てを摂ることができ、お茶殻も出ないので簡単に楽しんでいただけます。
夏場は冷抹茶もおすすめです。

-
一番茶の新芽が伸びだした頃、茶摘みの20日以上前から茶園に覆いをかけ日光を遮った茶園で柔らかく、緑色の濃い芽を育てます。
その新芽を蒸した後、揉みながら乾燥させたものが玉露です。
ふくよかな覆い香と、まろやかな旨みをもつお茶で、水色は鮮やかな緑色をしています。
お茶の旨み成分であるアミノ酸の一種テアニンが多く含まれています。
テアニンにはリラックス効果があります。
40℃から50℃に冷ました お湯でゆっくり淹れてください。夏場は冷水で淹れる 冷たい玉露もおすすめです。

-
覆いをしない茶園(露天園)で育てた新芽を蒸した後、揉みながら乾燥させたものが煎茶です。さわやかな香とほどよい苦味、後味の良さが特徴で、水色は品種にもよりますが少し黄色みがかった緑色です。
ビタミンCを多く含んでいます。
高級な煎茶は70℃から80℃に冷ました お湯でゆっくり淹れてください。

-
主に玉露を選別したときに出る茎の部分を中心にブレンドしたお茶です。
旨み成分テアニンが多く含まれ甘味とコクがあり、比較的淹れ方も簡単です。 夏場は冷水冬は高めの温度などお好みの淹れ方でお楽しみください。
おすすめは70℃前後です。

-
一番茶の葉の大きなものや二番茶を強火で炒って、香ばしく仕上げたお茶です。
炒ることにより カフェインの量が少なくなっています。

- 下級煎茶やかりがねに炒った玄米を混ぜたお茶です。
![[TSUEN TEA] ■宇治茶の老舗・通圓■](../site/img/common/logo.png)